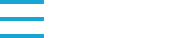副社長とアリさんマークの引越社との出会いについて教えてください。
実は、入社動機は不純なんです。今は副社長という肩書きをいただいていますが、引越社と出会う26歳のときまでは胸を張って言えるような仕事をしてなくて。ちょうど子どもができたタイミングでもあったので、しっかりと家族を養っていける会社に入ろうと、本屋で求人誌を読みながら転職先を探していました。それで、引っ越し業界ならフィットネス代わりにもなるなあなんて思いながら(笑)、某S社やA社、そしてアリさんマークの引越社に電話をして、家から一番近かった引越社へ面接に行ったのがきっかけです。面接で「引越社は実力主義」と言われて、「じゃあやってやろうやないか」と。
動機は不純だと仰いますが、いまや会社を守る立場。何を原動力として、現在まで会社を続けてこれたのでしょうか。
引越社は七転び八起きの会社。たとえ8回転んでも自分にその意思があれば、会社はいつでもチャンスをくれます。例えば、営業で結果が出せなければ、別の職種で頑張ればいい。別の職種で経験したことを元に、もう一度営業に挑戦したっていい。そういう会社なので、僕は今日までまっすぐ続けてこれたのだと思います。
困難にぶつかったとき、会社にとって一番大切な存在である社員を守ろうとして解決の仕方を失敗することもありました。一生懸命やって空振ることもありました。それでも、「やらせてみないとわからんやろ」という考えのもと、何度も挑戦させてもらえていることが僕のやりがいに繋がっています。
会社から「やらせてみないとわからんやろ」という言葉を最初にもらったのは、僕がまだ20代のとき。創業オーナーは、会社の財産である部下20~30人を当時まだ3年目くらいの若造である僕に任せ、2億~3億円の売上を上げてみろと言うんです。なんで僕にと聞くと、「やらせてみないとわからんやろ。ルールは会社で決める、だけど会社のルール内では好きなようにやれ」と。そんなことを言われたら、もう次の言葉なんて出てこないですよね。「じゃあやってやろうやないか」、ただそれだけです。
編集者の所感
些細なきっかけから始まった道を、やりがいへと変えられるかは自分次第。ときに困難にぶつかることがあっても、井ノ口副社長が強く前に進んでこれたのは、自分の正義を信じ、会社への恩義を忘れなかったからではないだろうか。「やらせてみないとわからない」とはいっても、きっと任せられない担当者には仕事を渡さないはず。井ノ口副社長の自分の正義を貫く勇気と強さが会社に伝わったのかもしれないと、ふと思った。
負けるときとは自分が諦めたとき
「勇」とは、正義を敢然と貫く勇気である。ときには嫌われ役に回りながらも、苦しい時期があっても、井ノ口副社長が踏ん張り続けてこられたのはなぜか。
昭和46年から続く会社を守るために、苦しい判断をしなければならない時もあったはず。過去の困難をどのように乗り越えてきたのでしょうか。
世間が思ってるほど、矢面にたつことに対してハードルが高いとは感じていません。起きてしまった事は現実ですから、受け止めて次にどうするかを考えます。全て、正しいことをなすためであり、会社を守るため。それが僕の役目だから。
副社長としてではなく、一般社員時代には結果が出ずに苦労したこともあったのでは?
もちろん、いただいたチャンスを全てヒットで返せたわけではないです。でも、悔しい気持ちがあったからこそ頑張れたし、くそーっ!と思っても引越社は何度もチャンスをくれました。あとは、自分の気持ち次第。例えば、お客様に引っ越しをご契約いただくまでに、契約、検討中、キャンセルというステータスがあったとして、検討中とキャンセルの境目ってどこだと思います?僕の感覚だと、お客様が「他社に引っ越しを依頼する」と言っても、僕が諦めない限り検討中なんですよ。「もう一度チャンスをください」と最後まであきらめない。僕は、仕事に対して全てそういう気持ちでやってきました。
編集者の所感
おそらく勇気とは、窮地に立った時に意識せずとも湧き出てくるもの。挑戦し続けることで備わり、他者に指摘されて初めて出会うものかもしれない。なぜ、井ノ口副社長は嫌われ役に回ることを恐れないのだろうか。それは、会社や社員、社員の家族といった“守るもの”があるからこそなのだろう。
半年後ではない、社員の5年後10年後を一緒に考える
「仁」の精神は、人としての思いやり、いつくしみの心のこと。副社長の社員に対する想いとは。
会社の財産だと語る、社員に対してはどのような想いを持っていますか。
会社がいかに社員を育てていけるか、これが本当に大事だと思っています。引越社ではドライバー、営業と決まった職種で入社しても、全ての職種を経験させるようにしていますが、これは一人ひとりに活躍の場を与えるため。営業職が少し苦手、デスクワークで活躍したいということであれば、内勤の仕事にも立候補できます。
会社は様々な歯車がないとまわりません。全社員が前を向いて働けるポジションを作ることが、会社を動かすことに繋がると考えています。
副社長が上に立つものとして、社員に対して立ち振る舞いで気を付けている事は何でしょうか。
会社の夢を語り、社員に目標を持たせるようにしています。入社する前から、「引越社でこれがしたい!」と明確な目標を持っている社員は少ないでしょう。ましてや、家族をすぐにでも養わなければいけない状況であれば、半年間の保証給が応募理由になることもあるはず。そういう社員に対して、入社してからどこを目指したいか、求めるのは地位なのかやりがいなのか、半年後ではなく、5年後10年後どうなりたいかを描かせるよう努めています。
管理職の方々にも意識させていることなどがあれば教えてください。
管理職に求めているのは、全社員にそれぞれ登れる階段があると部下に説明できること。社内の仕組みをしっかりと説明し、目標を持たせることができる支店長の下には、やはり人が残ります。上司が諦めたら終わり。支店長が部下の家族の生活を預かっているのも同然でしょう。部下に目的意識をしっかり持たせて進ませないといけません。入社理由は年収でも待遇でも構いませんが、半年後も仕事を続けたい、この人みたいになりたいと思ってもらえるような環境にしていってほしいですね。
編集者の所感
会社のために社員がいるのではなく、社員のために会社がある。だからこそ引越社では、仁愛の心をもって全社員が輝ける居場所を用意し、輝ける未来を想像させているのだという。正直、就活生として企業を見ているときは、自分にはどのような能力があって、どのような仕事が向いているかなど知る由もなかった。ほとんどの人が、会社に入ってから自分の能力を開花させるのだと、私は思う。そのための仕組みづくりや働きやすい環境整備というのは、やはり欠かせない。
自分の能力を活かして人の倍稼げる環境に
他者の気持ちを尊重することから生まれる謙虚さが「礼」。社員の意志を尊重した結果、引越社ではどのように労務環境を改善しているのだろうか。
今の引越社にはどのような社員の方が多いのでしょうか。
ずっと昔に比べれば、人の倍働いて人の倍稼ぎたい社員というのは少ないかもしれませんね。引越社では、入社してから半年間、保証給を支給しています。ほとんどの人が半年間の保証給が終わったあとの給与額について気にするけど、僕はね、6か月後に保証給と同じ金額を稼げるようになるにはどうしたら良いかを考えてた。でも、そういう社員だけでは会社は成り立ちません。上司にも、「自分と周りが同じ感覚だと思わないように」とよく言われていました。ただ、自分の能力を活かして人の倍稼ぎたい人は今の時代でもいるはず。一生懸命頑張れば稼げる、キャリアアップしていけるのが引越社の特徴です。
一生懸命頑張ればキャリアアップしていけるということですが、さらに詳しく教えてください。
引越社では、ドライバーも営業も社内試験に合格すれば、着実にキャリアアップを目指していけます。ドライバーであれば、2トン、3トン、4トントラックの試験を、営業であれば初級・中級・上級の試験を設けていますが、社員は職種に関係なく全ての試験の受験が可能です。管理職になるためには、一定の受験基準をクリアしてから社内試験を受験します。管理職試験を受ける時に提出しなければいけない書類があるのですが、僕は初出勤の日に「管理職用の書類をください」と言いました。ブロック長には、要注意人物として見られましたが(笑)。このように、何をすればキャリアアップしていけるのかについては社員に対して明確に示しています。
キャリアアップではなく、自分のペースで働きたい社員に応えるためには、どのような労務環境の改善を行っていますか。
労務環境の改善については、10年くらい前から取り組んできました。なので、昨今話題の働き方改革で示されている指針に対して、現在の引越社の労務環境はさほどずれてないと思っています。以前までは、月25日出勤ということもありましたけど、現在は現場に出ている社員でも月20日出勤が基本です。働きやすい環境を整えたというよりかは、10年かけて今の時代、自分のペースで働きたい社員に合わせたという感じでしょうか。社内の教育システムにおいてもルールにしても、今風の画期的なものを取り入れてるわけではないけど、全社員がやりたいことに対して柔軟に方向転換できるような環境です。やはり、引越社にとって社員が一番の宝物なので、労務環境については今後も改善の余地があるでしょう。
編集者の所感
一人ひとりのワークライフバランスを重視し、環境の改善を早い段階から着実に実現してきた引越社。社員を敬い、礼儀を尽くす気持ちをもつ引越社にとって、労働環境の整備はごく自然な流れなのかもしれない。最近、当たり前のように叫ばれている働き方改革だが、なかなか制度が浸透しない企業もある。そう考えると、「実現すること」がいかに容易ではないかが理解できるだろう。
部下を言いくるめた後のしっぺ返しは大きい
「誠」とは、言ったことをなす誠実さを表す。井ノ口副社長が、部下や仕事に向き合うときに意識している誠実さを探る。
副社長が仕事に対しても部下に対しても誠実であるために、日々意識している事があれば教えて下さい。
嘘をつかないこと、誤魔化さないことは、当たり前ですがどの立場になっても守らなければならないこと。部下を言いくるめることは簡単ですが、そのしっぺ返しは大きいでしょう。社内でも、インチキや子供だましな誤魔化しに対してはかなり厳しいです。支店はある程度自由な環境になっているので、悪いことをしようと思えばどうにでもなる。だからこそ、僕が九州や北海道へ行って養成講座を行ったり、社長が全国へ飛び回って社員と面談したり、社員教育は徹底しています。
お客様に対しては、どのような想いを持っていますか。
引っ越しは、お客様が何をもって満足するかが大事。こちらがどれだけプロの目線でやったとしても、お客様が満足できなければ意味がないです。自己満足な仕事では、「引越社=誠実」と評価されないでしょう。お客様が満足して初めて、周りの方にも引越社を紹介していただけるはず。誠実さとは、「紹介される仕事をする」ということが全てかなと。美味しい物を食べたら人に教えたくなりますよね。そういう仕事をしなさいと。これは、僕が入社したときからずっと言われていることです。
名古屋支店に勤めていた時、営業として担当エリアを回っていたのですが、「昔、引っ越してきたときにアリさんマークの引越社にお世話になった。娘が嫁ぐので、今度も引越社に引っ越しをお願いしたい」と、お客様から仰っていただいたことがありました。まさに、「紹介される仕事」の醍醐味ですよね。
編集者の所感
誠実さとは、偽りのない真面目さだけを表すのではなく、私利私欲のない真心を持つことも意味する。真心をもった社員がお客様に真心のあるサービスを提供することで、「紹介される仕事」に育つのではないだろうか。相手に感謝される仕事は、いつしか自分の心に誇りを生む。誇りが生まれると、謙虚さに陰りがでる。初心を大切にしたいと思いつつも、なかなか思い通りにいかないのが社会人の難しいところ…。
僕が働く目的は部下と変わらない
「名誉」とは、自分に恥じない高潔な生き方を貫くことである。井ノ口副社長にとって、名誉とは。誇りとは。
大手企業の副社長として、会社やご自身の働き方に誇りを持っている部分はどういったところでしょうか。
僕自身の働き方に誇りを持っているというより、自分自身が偉くなったと勘違いしたらあかんと、自分にも部下にも伝えています。僕含め役員が会社の方向性を決めて舵取りしますが、現場でダンボールを運んでくれている社員、お客様相手に汗水流してくれる社員達がいるから会社が成り立っているので。そういう意味では、一生懸命頑張ってくれている社員が会社の誇りになりますね。
井ノ口副社長は、なぜずっと謙虚な気持ちを持ち続けられているのでしょうか。
サラリーマンだから。自分が起業した訳ではなく、僕は引越社でずっとご飯を食べさせてもらっているので。僕は自分が生きていくために、ご飯を食べていくために仕事を頑張っている。その目的は、社員と変わらないですよね。営業、ドライバー、幹部どの立場の社員にも、僕とあなたは一緒だよと伝えています。僕もあなたと同じ経験をして、人よりもほんの少し努力した結果、副社長というポジションで仕事させてもらってるということだけです。
編集者の所感
周りから見れば誇り高い存在であっても、当人は自分を見つめなおすことを忘れていない。謙虚さはいつになっても持ち続けるべき感情なのだろう。驕ることなく着実に未来へのビジョンを描くことが、実現への近道なのかもしれない。
孫の代まで続く会社を目指して
「忠義」とは、主君に対する絶対的な従順。井ノ口副社長の主君が会社であるとすれば、未来に向けてどのようなビジョンを描いているのだろうか。
アリさんマークの引越社の未来に向けたビジョンについて教えてください。
全国に営業所をつくりたいですね。引越社は上場こそしていませんが、自社ビル、自社のスタッフ、自社のトラックを使って「どこを切っても同じサービスを提供する」というスタンスで今日まで社会に貢献し、高い評価をいただいています。
ただ、ほとんどを自社で行っている分、展開スピードが遅いのがデメリット。「自分の故郷に営業所が欲しい」と、社員アンケートで意見をもらうことがあるのですが、未だに叶えられないのが本当に悔しい。社員が何らかの理由で地元に帰るとなった場合、その土地に営業所があれば異動という形で仕事を与えられますが、営業所がなければ辞めるしかありません。
僕が入社したときに仕事を教えてくれた現場の責任者が、ある日、腰痛でドクターストップを受け、現場の仕事ができなくなりました。その責任者は、現場も営業も頑張る人でしたが、なぜだか営業がからっきしダメ。現場も営業もできないとなると、当時は会社を辞めるしかなかった。その時に、新人ながら当時の上司に「あの責任者はなぜ会社を辞めないといけないのでしょうか」と聞きました。そうすると上司は、「私もそう思います。井ノ口くん早く2人で頑張って会社を大きくしましょう、会社を大きくすれば彼でもできる仕事があるはずです」と。僕は、その言葉が今でも忘れられないんです。
現在、東京本部は部署が多いので、現場ができない社員でも仕事がありますが、九州や北海道などはまだ十分ではありません。模索しながら働きやすい会社作りに取り組んでいますが、描いてきたもの、継続してきたものを絶やさないように、これからも進み続けたいですね。部下に夢を見せる、どこをとっても一定レベルのサービスが提供できるようにする、全てですけど、創業オーナーが言っていた「孫の代まで続く会社、孫が勤めたいと思う会社にしなさい」という言葉は、昭和46年創業時から今でも脈々としています。これからも、引っ越し業界の先頭を走る会社として、培ってきた歴史の中で学んだことを活かしながら、新しい時代に挑戦していきたいですね。
編集者の所感
会社に対して忠義を尽くしているにも関わらず、どうにもできない理由で会社を辞めなければいけないことほど切ないことはない。井ノ口副社長が描くビジョンは、そんな過去の体験から生まれたもの。過去のどんな苦労も栄光も、決して無駄なことはないと感じた。
アリさんマークの引越社は、もう前進している
昭和46年創業以来の会社の在り方を守りながらも、現代に合わせて前進してきた引越社。その前進を支えてきた井ノ口副社長は、常に自分を信じて戦ってきた存在であり、誰もが簡単に真似できるような歴史を辿ってはいない。それでも、全ては自分の考え方次第でどうにでもなるのだと、現在のアリさんマークの引越社には誰もが輝ける場があるのだと強く語る。井ノ口副社長が語った「7つの徳」は、現代を生きる社会人にとっても学べることが多いのではないだろうか。もうアリさんマークの引越社は、あの日のままで立ち止まってはいないのだ。
引越社HPで社内の待遇や求人について確認する
フリーダイヤルで問い合わせる
アリさんマークの引越社の転職/採用について

アリさんマークの引越社はここ3年で大きく労働環境が変わりました。それに伴い給料など採用情報も大きく改善。
当サイトではそんな条件を3年前と徹底比較しています。また、現在の募集要項を紹介し、直接アリさんマークの引越社に問い合わせもできるようになっております
新卒の方や転職、求人を探している人は必ず確認してください。
アリさんマークの引越社の就職
(新卒・転職採用)情報を
3年前と比較!給料や転職の評判も!
アリさんマークの引越社の会社情報
アリさんマークの引越社の
会社情報について更に詳しく